常識VS常識
こんにちは。
ファミリーサポートのしゅううです。

みなさんは、
フルーツの「なし」
と言われると、何色を思いうかべますか?
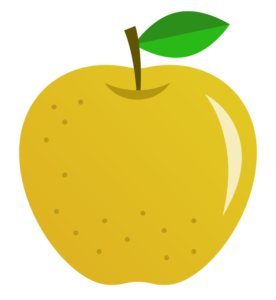
こんな色を思いうかべましたか?
この「なし」を思いうかべたら、日本育ちだとおもいます。
オーストラリアで「梨」は
Pear 「ペア」
と言います。
日本だと「洋ナシ」と呼ばれています。
オーストラリアで生活している子供に
同じことを聞くと、
なし=洋ナシ
となるため、
フルーツの「なし」は何色?
と聞くと
「みどり」「きみどり」
と答えます。

どちらも正解ですよね。
ただ、育った環境が違うため、
答えが違うだけです。
そもそも日本語で
「なし」=「梨」
のため、そこには海外からはいってきた
「洋ナシ」は選択肢にはいらない。
洋ナシ≠梨
なんですね。
ここオーストラリアでは、
もちろん日本ではないので、
日本の常識、日本の当たり前は
オーストラリアの常識、オーストラリアの当たり前ではありません。
例えば、野菜。
きゅうり、ナスのサイズは日本のものに比べ、3倍ぐらいあります。
りんご。日本のものに比べ、一回りぐらい小さいものが主流です。
オーストラリアでは、りんごを皮ごとまるかじりをする子供を多く見ます。(うちの子もします)
日本のりんごは、食べきれないぐらいでかいですし、
皮をむいて、切り分けるのが当たり前ですよね。
私は日本でりんごをまるかじりしたことはありません。
歯ぐきから血が出るから。という理由ではありませんよぉ。
日本との違いに親がまず気づいて
それを子供に伝えていく。
価値観の違い
文化の違い
それらが構成する
「当たり前」「常識」
私の子供も、私の常識とは異なった常識の中で
成長をしています。
このポイントをおさえ、
お互いに日本とオーストラリアの文化を理解できるように、
子供と一緒に成長をしていく。
ここがバイリンガル教育に大切なこと!!
と思っている次第でございます。